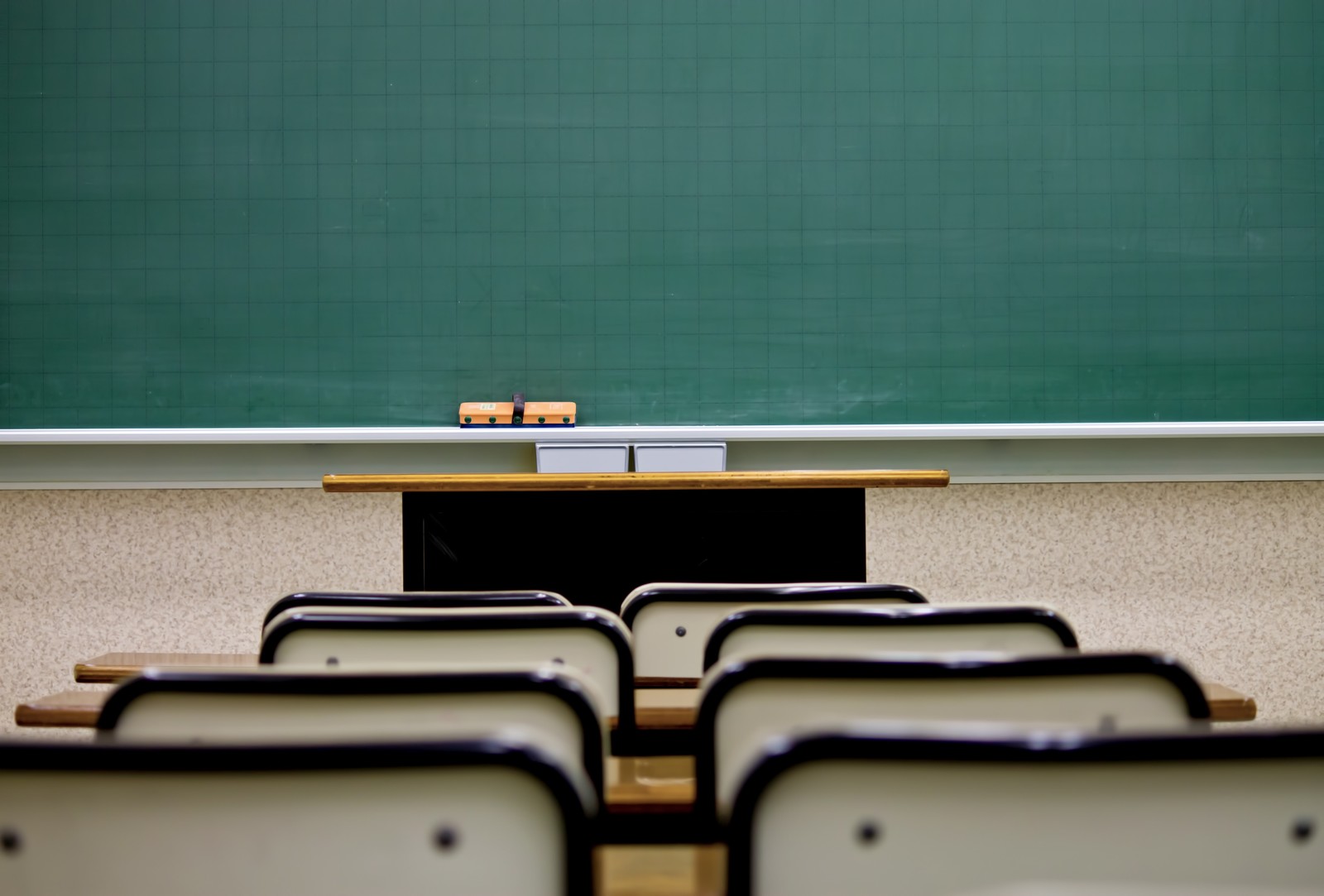All Aboutに、「中学受験で「最後に伸びる子」と「成績が上がらない子」の違いとは?」という記事が掲載されています。

この記事の内容ですが、私が今までの経験で感じていたことと合致しており、的を射ていると思います。
特に、「中学受験で最後に伸びる子の共通点1:楽しんで受験勉強をしてきた子」の中の、
一方、塾講師の厳しい指導や母親の懸命の働きかけで、内心嫌々ながらも必死に勉強してきた子も、確認テストや模試で結果を出すことを目標に日々勉強に取り組んでいます。テストで点数を取るという明確な目標があるため、マジメに取り組めば点数には結びつきます。
ただ、小6の夏以降の模試は出題範囲の単元が限定されていない総合問題になり、表面的にしか理解していなかったり、暗記に頼ったりした勉強では点数が取りにくくなってくるのです。
出典:All About「中学受験で「最後に伸びる子」と「成績が上がらない子」の違いとは?」
については、その通りだと思っています。
そして、現在小5の長女もどちらかというとこれに近い状況になっていないか、正直不安になっています。
長女の場合、嫌々ながら勉強している訳ではありませんが、特に算数など、直近でやった問題と同じ問題形式であれば解き方を記憶しているので解けるが、応用問題になると対応できない場合があるからです。
それって、「こういう問題の場合はこういうやり方で解ける」といった表面的な理解に留まっているということなので。
本来は、その根底にある考え方、原理を理解することで、応用できるようになるのですが、そこまではなかなか難しいという状況です。
教える際には、なるべく図などを使って、なぜそうなるかを教えるようにしていますが、自分で学習している際には、そういった理解にまでは及んでいないように感じています。
本当は、そういう根底のところを塾の授業で教えて欲しいのですが、限られた授業時間の中では、解法の説明中心になってしまっているんでしょうかね。